「墓じまい」について教えて!

墓じまいとは、自分や家族のお墓を処分し「更地」にして「墓地を返却」することです。(※「墓じまい」と「離壇」は別です)墓じまいを考える理由はさまざまですが、主なものは以下のようなものです。
・墓石の維持費や管理費が高くて負担になっている
・子どもや孫に負担をかけたくない(もしくは居ない)、または遠方に住んでいて墓参りに来られない
・自分の死後にお墓が「無縁墓」になるのではないか、心配している
・自分の遺志として「先祖代々のお墓」に入りたくなく、火葬後に散骨や樹木葬にしたい
墓じまいをする前に知っておくべきこと

墓じまいをする前に知っておくべきことは、以下の6つです。
- 家族や親族の同意を得る
- 墓じまい後の供養方法を決める
- 墓地の返還手続きをする
- 役所に改葬許可を申請する
- 魂抜き(お性根抜き)をしてもらう
- 解体撤去工事をする石材店を決める
※寺院などの「墓じまい」時には上記とは別に、「離壇(寺院なのどの檀家をやめる事)」の手続きが必要です。
もっと詳しく教えて!
それぞれの詳細は次のようになります。
- 家族や親族の同意を得る
墓じまいは家族の大きな決断です。事前準備をしておかなければ、後からトラブルになることもあるので注意しましょう。現在のお墓の状況を確認しておくことが大切です。お墓は、家族や親戚など、周囲の人たちもおのおののタイミングで自由にお参りできる場所でもあります。こうした人たちへの配慮を怠ってしまうことで、「お墓参りに行ったらお墓がなくなっていた」「どうして教えてくれなかったの」などと苦言を呈され、トラブルにつながる恐れがあります。墓じまいの必要を感じたら、ひとりで判断するのではなく、まずは家族や親戚たちに相談して、意見を求める、同意を得るなどのステップを踏みましょう 。 - 墓じまい後の供養方法を決める
墓じまいでもっとも大切なことは、その後の供養です。お墓の中の遺骨を取り出したあと、その遺骨をどこに移すのかをしっかりと検討しましょう。選択肢として挙げられるのは「新たに墓石を建立する」「納骨堂」「樹木葬」「散骨」「永代供養」などです 。これらの違いについては下で詳しく解説します。 - 墓地の返還手続きをする
墓じまいの方針が決まったら、墓地の管理人に、いまあるお墓を解体撤去する旨を伝えます。管理人とは、公営霊園や民営霊園の場合は霊園管理事務所、寺院墓地の場合はお寺の住職、地域の墓地の場合は自治会長などです 。 - 役所に改葬許可を申請する
改葬先のお寺や霊園に遺骨を納めるには「改葬許可証」が必要です。改葬許可は、改葬元の役所に申請をします。窓口やウェブサイトから書類を入手し、必要事項を記入します。加えて、改葬元の墓地管理者から埋葬の事実を証明するための署名や捺印を、改葬先の墓地管理者からお骨の受け入れを証明するものを入手し、これらをまとめて役所に提出します。必要書類や申請方法は、自治体によって対応が異なりますので、直接確認してみて下さい 。 - 魂抜き(お性根抜き)をしてもらう
墓石の解体撤去工事に入る前に、僧侶(ご住職)にお性根抜きの供養をしてもらいます。墓石には仏さまやご先祖さまの魂だけでなく、長年家族たちが手を合わせてきた「想い」や「念」も込められています。お性根抜きとは、こうしたものに対する感謝と敬意を示す儀式だと考えられます 。中にはお性根抜きを不要と考える人も居るかもしれませんが、石材店によってはお性根抜きのされていないお墓だと、解体撤去に応じてくれないところも少なくありません。 - 解体撤去工事をする石材店を決める
石材店を決める際は、下記を参考にしてください。- 墓じまいの実績があるか
- 流れや手順を分かりやすく教えてくれるか
- 改葬先のお墓探しへのサポートがあるか
- 霊園や寺院とのやりとりに対してアドバイスがあるか
など、総合的に信頼できる石材店かどうかを見極めましょう 。

相談店舗
お仏壇のご相談は下記店舗までご連絡ください。

この記事を書いた人
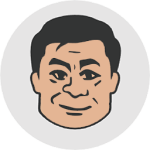
座右の銘は「先駆け」。マイブームは休みの日に愛犬を連れて行くドックラン巡りです。


