ペットへの「遺産」を残すことはできますか?

引き取り手のないペットの数が増えている
ここ数年、高齢の方が飼育していた引き取り手のないペットの数が増えているのはご存知ですか?その理由として下記の様なことが挙げられます。
・飼い主が亡くなった
・年をとりペットを飼いきれなくなった
・老人ホーム、介護施設などに入居をする
・病気などで長期入院などを余儀なくされた
・認知症などでペットの世話などができなくなった
・都市部の子供の家(ペットが飼えないマンションなど)に引越す
理由はそれぞれですが、その時の準備をしておかないと愛するペットが不幸になりかねません。
ペットのための終活がペットを救う
準備なく突然に飼い主が居なくなったり、亡くなった場合、引き取り希望者がいないことが多いそうです。ペットは保健所に引き取られ、そこで新たな引き受け先が見つからなければ、最終的に「殺処分」されてしまいます。
そんなことにならない為に、「ペットのための終活」をおすすめします。ペットの為の終活を行う事によって、もし自分に何かがあっても、ペットを守ることが出来るのです。
引き取る里親の負担を減らす
ペットのための「終活」でまずすることは、引き取る側のことを考えて、ペットの情報を残して置く事です。ペットの詳しい情報が得られないと、引き取る里親も困ることが多く引き取り率も下がります。
その情報とは、
・ペットの名前
・種類(犬種、猫種、鳥種など)
・性別
・年齢
・登録情報(役所への登録内容・マイクロチップなどの登録内容)
・予防接種の記録
・かかりつけの動物病院情報
・健康状態
・病気の有無(持病や過去にかかった病気など)
・薬などの有無(常に飲んでいる薬やサプリメントの種類と摂取の理由)
・性格や特徴
・食べさせている餌のメーカーや銘柄
・好きな食べ物
・嫌いな食べ物
・食べさせてはいけないもの
などをきちんとまとめて記録し、書面で残しておきましょう。
ペットの寿命が近そうなら、お迎えがきたときにどうしてほしいのかについても伝えるべきです。事前に用意しているペット墓に埋葬してほしい、あるいは自分のお墓に一緒に埋葬してほしいなどの希望があるときも、きちんと書面で残しておきましょう。
ペットのために飼育費を残す!「負担付遺贈」

親族や友人の中で里親になってくれそうな人がいるときは、ペットにかかる養育費を準備しておき、そのことを伝えておきましょう。
また、ペットの世話をしてもらうという条件付きで、相応の遺産を取得してもらう「負担付遺贈」という方法もあります。
負担付遺贈とは、遺言により受遺者(財産をもらう人)が「財産を受け取る代わりに、一定の義務を負担する」ことです。
飼い主(遺贈者)はペットの世話をしてほしい人を選び、「財産を贈る代わりにペットの世話をしてください」という内容の遺言書を作成してください。
そんな解決法として、「ペット信託」があります。
ペットの飼育費としてお金を残す事ができるのです。
飼育費がちゃんと適切に使わているか、ペットが適正に飼育されているかを確認してもらうため「信託監督人」として、行政書士などを選任することもできます。
老犬ホーム・里親制度

もし事前に、引き取ってくれる人がみつからないときには、里親制度や老犬ホームという方法もあります。
ただし里親制度は子犬でなければだめなど制限のあるところも多いので、かかりつけの獣医に「里親制度」 について尋ねてみたりインンターネットで近隣で利用可能な制度を探してみるのなどもよい方法です。
また10 年ほど前より「老犬ホーム」が登場し、少しずつ利用する人が増えてきました。よいホームかどうかの判断が難しい部分もありますが、獣医や信頼できるトリマーなどから情報を得て実際にいくつか訪ねておくと良いでしょう。
また最近では、老犬ホーム・老猫ホーム情報がまとめられた、ホームページ【老犬ケア】で簡単に検索できます。
頼みたいと思うところを探しておくと自分がいなくなった後の心配はかなり減らせるでしょう。
※サライjp「自分がいなくなった後が心配…。知っておきたい「愛するペット」の上手な遺し方」より一部転載
もしもの時のためにも、愛する家族(ペット)の終活を行っておけば、安心してペットと共に過ごせることでしょう。
この記事を書いた人
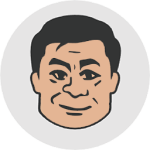
座右の銘は「先駆け」。マイブームは休みの日に愛犬を連れて行くドックラン巡りです。


